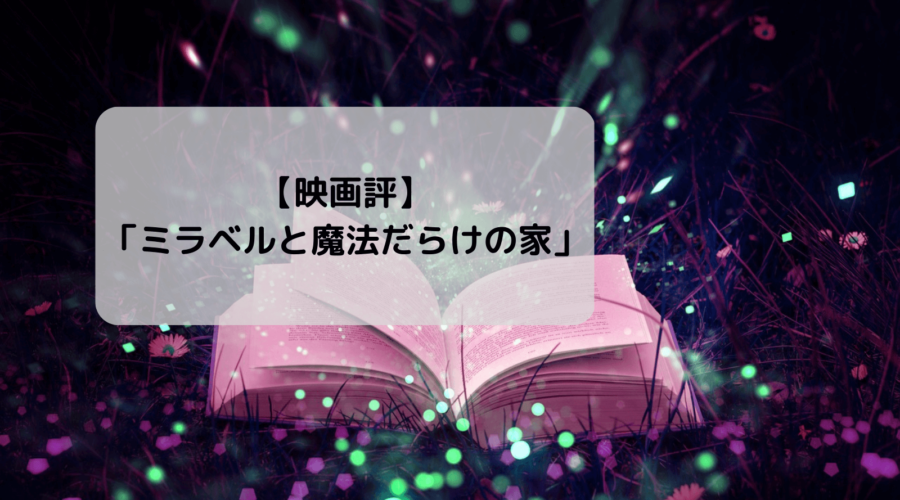【映画評】「ミラベルと魔法だらけの家」
「ミラベルと魔法だらけの家」感想・レビュー
2021年に公開された映画『ミラベルと魔法だらけの家(原題:Encanto)』。ディズニー映画ならではの繊細な映像とポップな音楽の数々はいつも通り。ただ、この作品が他のディズニー映画と違う点は、分かりやすい悪役(ヴィランズ)がいないことだ。
代わりに、この作品の“悪”となっているのは“魔法”とも言えよう。登場するマドリガル家の人々は、皆ひとりずつ特別な魔法の力を持っている。ただ1人、主人公のミラベルを除いて。魔法の力を持たない者として、ミラベルは家族からどことなくよそ者扱いされてしまっている。彼女がいない時に家族写真を撮ることを誰も気にしていないし、魔法の力が弱まって家に大きくヒビが入った時には彼女のせいにされる始末だ。
一方、物語が進むにつれて、魔法の力を持つ家族たちもまた、それぞれ悩みを抱えていることが分かってくる。「花の魔法」を持つ美しいイサベラは、「完璧でいなければ」という想いから自分の素直な気持ちを押し殺していて、「力の魔法」を持つルイーサは、「もしこの力が無くなったら自分の価値は無い」と不安と戦いながら生きている。各人に与えられた魔法は、その人を象徴するものである一方で、足枷でもあるのだ。
映画では「魔法があるかないか」という分かりやすい表現になっているが、「魔法=特技」と置き換えれば、現実世界でも同じことが言える。特技を持つ者はそれを生かして人に貢献しなければと悩み、特技が見つからない者は自分には価値がないと悩む。そして、この物語が伝えたかったのは、「魔法(特技)の有無は関係ない」ということだと思う。生まれてきただけで私たちは価値のある存在で、何かに縛られて生きていく必要はない。劇中では、全員がそのことに気づいたところで、マドリガル家は本当の意味で「家族」になる。
冒頭でこの作品の“悪”は魔法と書いたが、言い換えれば“悪”は自分自身の心に存在するといったところだろうか。自分でつくりだした“悪”に支配されず、ありのままに堂々と生きていきたいものである。